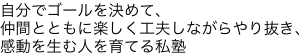塾長のプロフィール
ひなみ塾塾長
黒川裕一(くろかわ ゆういち)
1972年生まれ。熊本市出身。
東京大学法学部卒業後、22歳で渡米。インディ系の映画製作に携わりつつ、1997年にコミュニケーション学修士号を取得(映画専攻)。
2003年、世界最大の脚本コンテストであるサンダンス・NHK国際映像作家賞の最優秀作品賞候補にノミネート。 アメリカ長期滞在の経験を生かし、映画のみならず大学のテキストなど語学関連の書籍も多数執筆。(2022年現在21冊)
2001 年秋、「故郷熊本をもっと元気に」 との願いを込め、 「自ら気づき、 仲間と学び、 社会で動く」 ことのできる人財の育成を目的に活動開始。
2002年には同活動の受け皿として「NPO法人ツムリ30」を設立。英語と映画を教材にした学びの実験室である「電影えいご室」(参加者のべ4000人)などを経て、2004年12月に総合コミュニケーションスクール「ことばの学校」を開校。
限定の講座に、関東、関西地方からの遠距離受講者も多数
。2006年には、「学ぶたのしさ、のびるよろこび、仲間との絆の深まり」を理念とした、「六秒塾」(現「ひなみ塾」)を開講、現在、小学校に入る前から一生学べる全17クラス、280名の塾生を抱え、全てのクラスを自ら教えている。